日本の歴史
日本のチョコレート事始め(チョコレート最初の文献)


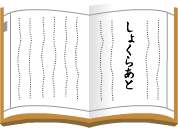
日本のチョコレート事始め
日本にチョコレートが伝わったのは江戸時代のこと。外国(オランダ・中国)との交易の窓口であった長崎に、チョコレート伝来の記録があります。
寛政9(1797)年3月晦日 長崎の遊女が“しょくらあと”を貰い請ける
長崎の著名な遊女町であった丸山町・寄合町の記録『寄合町諸事書上控帳』に、寄合町の遊女大和路が、出島の阿蘭陀人から貰い請けて届け出た品物の中に、“しょくらあと 六つ”の記載があります。これが史料に記された日本で最初のチョコレートです。
長崎出島の阿蘭陀人は帰国に際し、使い古した蒲団や道具類などを遊女に与えており、それらは当人に払い下げられました。『寄合町諸事書上控帳』は失われた部分も多く、この日以外にもチョコレートを貰い請けたり、届出をしなかったものもあったと考えられ、長崎ではチョコレートは異国の珍品として知られていたようです。
-
寄合町諸事書上控帳
『寄合町諸事書上控帳』の記事
覚
1 硝子瓶三つ
1 紅毛きせる 拾五本
1 紅毛蠋 三拾壱挺
1 しょくらあと 六つ
1 蜜漬 三壷
1 くて塩入 弐つ
1 紅毛蝋燭立 弐つ
1 火鉢 壱つ
但ししん切添
1 さほん大小弐拾壱
1 同櫛箱 壱つ
1 こをひ豆 壱箱
1 皿紗古蒲団 三つ
但鉄小箱
内壱つ不足
1 ぽをとる入角ふらすこ 壱つ
1 こ津ふ大小六つ
1 酒入同 六つ
1 ちゃん板 拾五枚
右之桁々阿蘭陀人より私抱遊女大和路貰請候処、相違無御座候依之御渡被成慥に請印取申候、早速同人江 相渡可申候、然上は、右品之内若余人江 売渡候儀も御座候節は、申出売渡書付申受候様可仕候為 其印形仕置候。 以上
巳 三月晦日
筑後屋平右衛門印
芦刈茂次之助殿
寛政12(1800)年 「長崎聞見録」に“しょくらとを”が紹介される
寛政年間に2度、足かけ6年にわたり長崎に遊学した、医術や動植物に造詣の深かった京都の人廣川獬が、長崎滞留中に見聞したこと、調査したことを寛政9(1797)年に書きまとめ、寛政12年に『長崎聞見録』として刊行しました。紹介された多くの文物の中に、“しょくらとを(チョコレート)”があります。
-
長崎聞見録
『長崎聞見録』の記事
しょくらとをは。紅毛人の持渡る腎薬にて。形獣角のごとく。色阿仙薬に似たり。其味ひは淡なり。其の製は分暁ならざるなり。服用先熱湯を拵へ。さてかのしょくらとをを三分を削りいれ。次に鶏子一箇。砂糖少し。此の三味茶筅にて。茶をたつるごとく。よくよく調和すれば。蟹眼でる也。是を服用すべし。
慶應4(1868)年8月3日 徳川昭武がシェルブールでココアを喫す
1867年にパリで開催された万国博覧会に幕府代表として赴いた15代将軍徳川慶喜の弟の水戸藩主徳川昭武は、各地を歴訪後パリで留学生活を送っています。『徳川昭武幕末滞欧日記』に、この日フランス・シェルブールのホテルにて“朝8時、ココアを喫んだ後、海軍工廠を訪ねる”と記しています。文献にあらわれる最初のチョコレート(ココア)の体験で、江戸時代最後のチョコレートの記録です。
-
「しょくらとを」は阿蘭陀人の私物
「しょくらとを」は阿蘭陀人の私物
江戸時代を通じて、阿蘭陀船、唐船などの輸入品目や幕府からオランダ商館あて注文書にも“チョコレート”の記録はありません。“しょくらとを”は公式な輸入品ではなく、阿蘭陀商館員が自己使用のために持込んだ物が遊女への払い下げ品(貰い品)として流布したもので、量的にも少なく大変珍しいもので、長崎だけに知られていたと考えられます。
